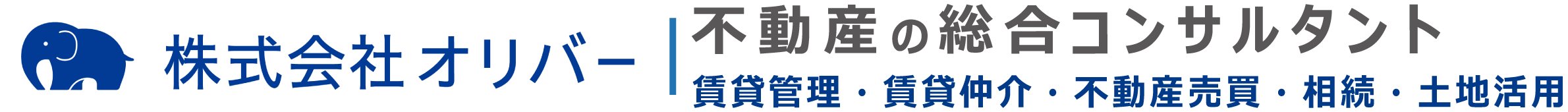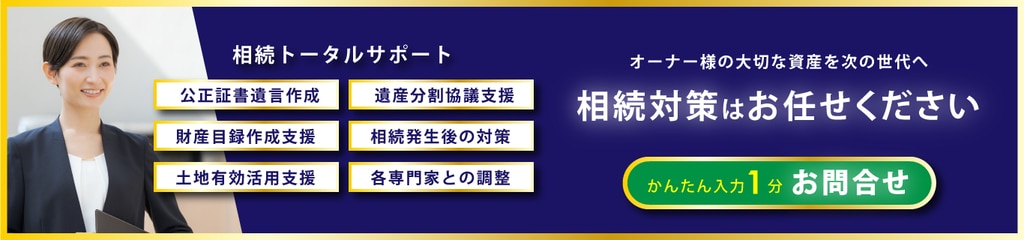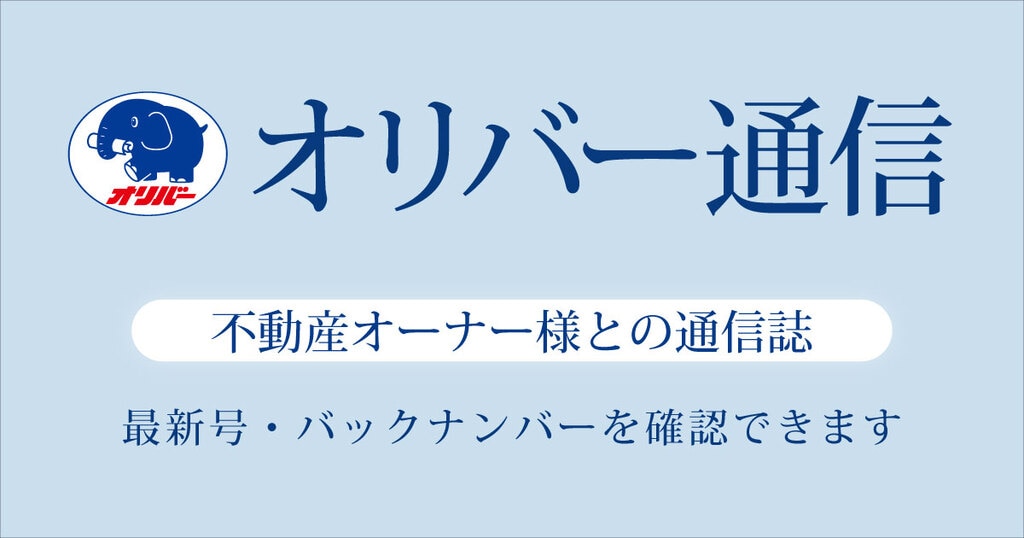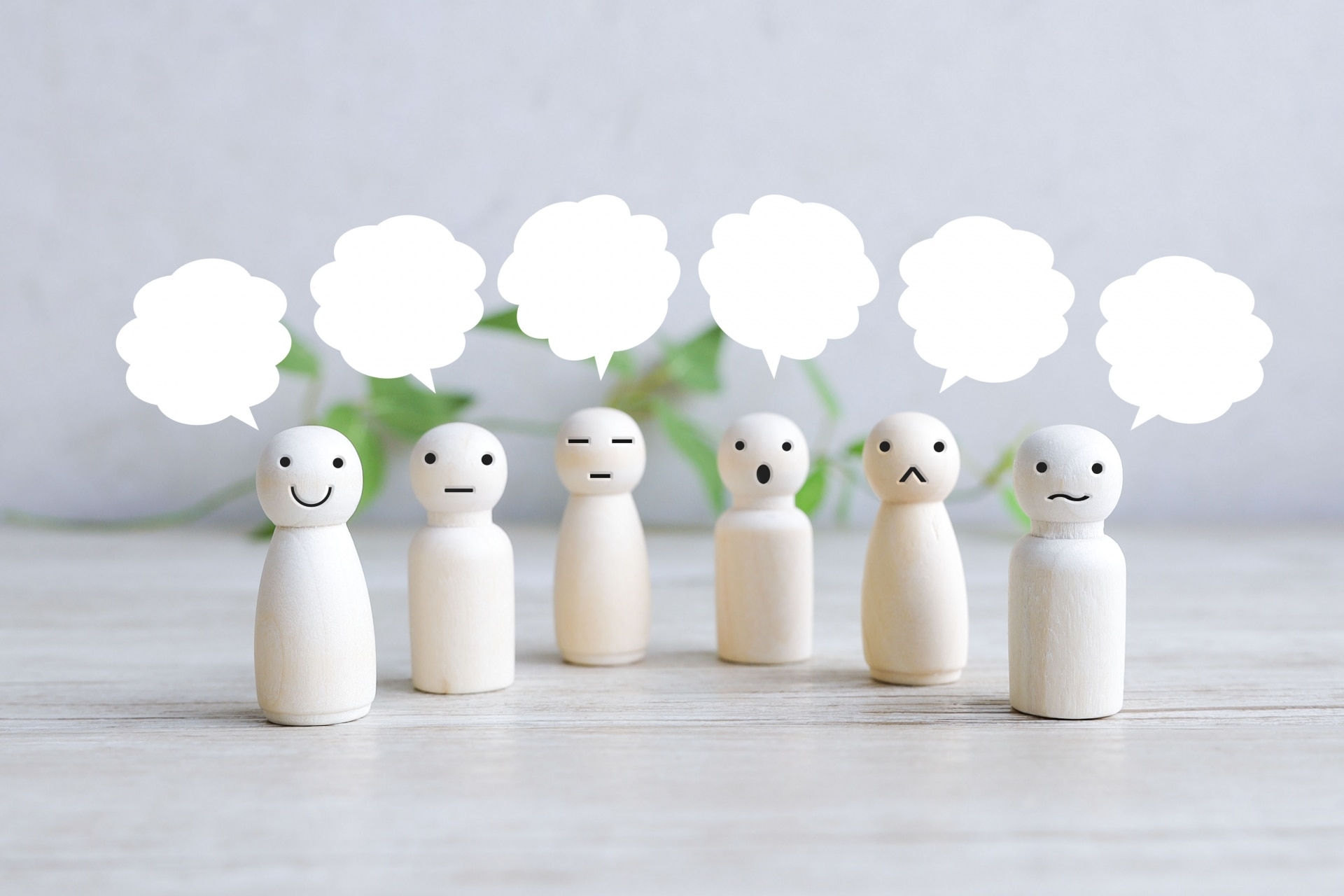
事業承継でトラブルになりやすい「遺留分」とは Part2 |相続
<目次>
事業承継で遺留分トラブルを避けるための主な対策
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
今回は、『事業承継でトラブルになりやすい「遺留分」とは Part1』の続きで、『事業承継で遺留分トラブルを避けるための主な対策』についてお話しします。
(Part1からご覧ください)
対策1.遺言書の作成
遺言書は、経営者の相続が発生したときに、経営者が所有している自社株式や事業用資産を後継者に取得させる有効な方法の一つです。
スムーズな事業承継のためにも、経営者は遺留分を考慮した遺言書を作成し、遺留分侵害額請求を回避する手立てを講じておくとよいでしょう。
主に相続対策で使われる遺言の種類は、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」です。遺言の実行性を考えると、公正証書遺言がいいでしょう。公正証書遺言は公証人が関与するため、形式不備等により無効になるおそれがありません。
また、原本は公証役場にて保管されるため、紛失、隠匿、偽造のおそれがなく、家庭裁判所による検認手続きも不要です。
対策2.遺留分の事前放棄
後継者以外の相続人は、被相続人の生前に自分の遺留分を放棄できます。
しかし、遺留分を放棄するには、後継者以外で遺留分を放棄しようとする相続人が自分で家庭裁判所に申立て、許可を受けなければならないため、それら相続人にとっては手間がかかります。
また、相続人に遺留分放棄に協力してもらうための理解を得ることが重要です。
対策3.遺留分に関する民法特例の活用
事業承継における遺留分トラブルを防ぐ方法として、遺留分に関する民法特例(経営承継円滑化法の民法特例)を活用する方法があります。
民法特例1.除外合意
除外合意とは、後継者と他の相続人の間で、後継者が経営者から生前贈与等によって取得した自社株式を遺留分算定の基礎財産から除外できます。
これにより、他の相続人は遺留分を請求できなくなるため、相続人トラブルのリスクを回避し、自社株式の分散を防止できます。
民法特例2.固定合意
固定合意とは、後継者と他の相続人の間で後継者が経営者から生前贈与等によって取得した自社株式について、遺留分算定の基礎財産に算入する価額を合意時点の価額に固定することができます。
固定合意を適用すれば、自社株式が将来価額が上昇しても遺留分への影響がなくなるため、相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。
ただし、固定する合意時の時価については、合意時に相当な価額であることを税理士、公認会計士、弁護士などの専門家に証明してもらう必要がある点に注意が必要です。
おわりに
オリバーでは、今回の遺留分の主な対策の一つであります「遺言書の作成」を含め、 相続の基礎から分かりやすくご説明をする相続対策基礎セミナーを定期的に開催しております。参加費は無料です。是非、ご参加ください。
また、個別のご相談も承っております。提携の司法書士や税理士と連携して相続手続きを支援しております。相続手続きに関するご不明点や手続きのご用命などございましたら、いつでもご連絡ください。