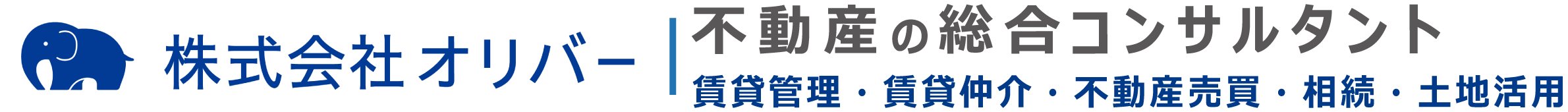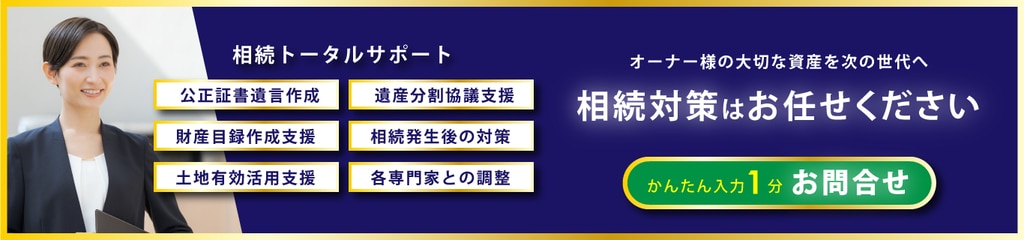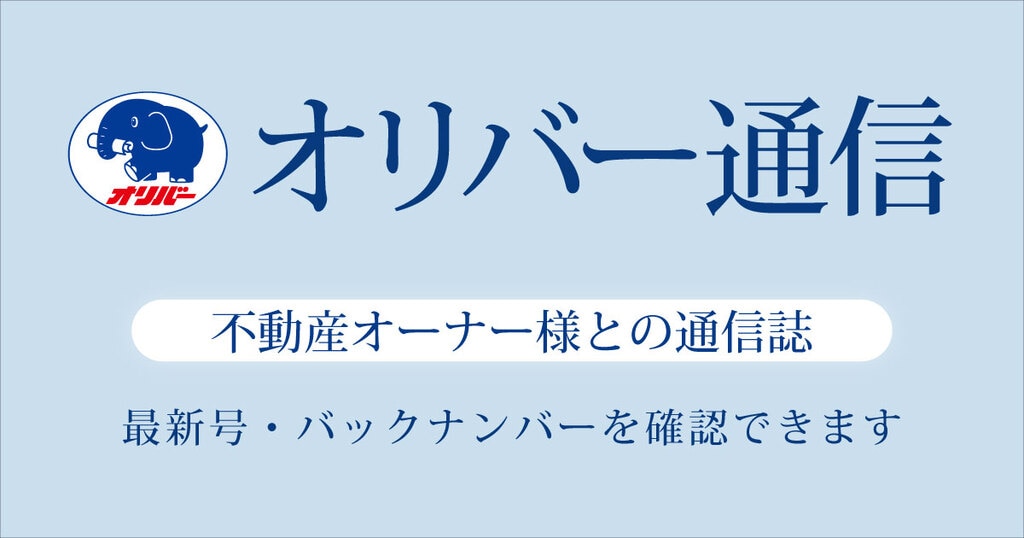令和6年贈与税制の改正を踏まえて贈与をどうする?Part2|相続
目次[非表示]
- 1.はじめに
- 2.贈与税制改正後の贈与方針
- 3.最後に
はじめに
今回は、「令和6年贈与税制の改正を踏まえて贈与をどうする?Part1 」の続きとして、贈与税制改正後の贈与方針についてお話しさせていただきます。
(Part1からご覧ください)
贈与税制改正後の贈与方針
前回の改正内容から分かる通り、暦年課税制度は加算期間が3年から7年に延びることにより、節税効果が低くなったといえます。
この生前贈与加算を受けるのは、「相続又は遺贈により財産を取得した者」で、通常は法定相続人です。したがって、法定相続人への暦年贈与は活用しづらくなったということです。
「相続又は遺贈により財産を取得した者」以外に対しては、これまで同様に生前贈与加算はありませんので、贈与した瞬間に節税効果が得られます。代表的なケースは孫への贈与です。
また、相続時精算課税制度の適用を受ければ、110万円以下の贈与部分は、贈与した瞬間に節税効果を得られることになります。
このことから、今後は贈与する相手によってどちらを使うのかを選択することが、税務上は効果的だと言えそうです。
一般的な考え方としては、特に贈与者が高齢である場合は以下の通りとなるでしょう。
1.子(18歳以上)への110万円贈与
相続時精算課税制度を選択して、年間110万円までの財産を贈与します。
初めて相続時精算課税制度を選択する場合は、原則として、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者が納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この提出を忘れると、自動的に暦年課税制度を選択したことになって相続開始前7年分の贈与財産が相続税の課税対象となりますので、ご注意ください。
なお、令和5年以前に既に相続時精算課税制度を選択している場合であっても、令和6年以後の贈与分からは年間110万円以下の部分については申告不要です。
2.孫への贈与
暦年課税制度を使って贈与します。
孫は基本的に生前贈与加算の対象外ですから、富裕層の方であればある程、年間110万円という基礎控除額にこだわらずに積極的に贈与して、相続財産を減らすことによる効果を追求したいものです。
ただし、次のようなケースでは孫も生前贈与加算の対象となるため注意が必要です。
イ)法定相続人(「孫養子」「代襲相続人」)である
ロ)遺言等により財産の全部又は一部を取得する予定である
ハ)保険金受取人となっている
この場合、孫が18歳以上であれば、1.と同様に相続時精算課税制度を選択して年間110万円までの財産を贈与する方が確実でしょう。
1.と2.は、あくまでも一般論です。ケースによっては、これとは異なる贈与方法を選択した方がより高い効果が得られる場合もあります。
判断のポイントになるのは、贈与者の「年齢」「家族構成」「財産内容と財産額」「将来の遺産分割案」などです。
最後に
贈与は数ある相続対策の中でも、最もポピュラーで、どなたにとっても活用しやすいものです。ただし、失敗しても後からやり直しがききません。今回の改正により贈与方法の選択は格段に難しくなりましたし、他の様々な特例とどう組み合わせて活用するのかなども検討が必要です。失敗しないために、専門家への相談が不可欠と言えるでしょう。
オリバーでは、 相続の基礎から分かりやすくご説明をする相続対策基礎セミナーを定期的に開催しております。参加費は無料です。是非、ご参加ください。
また、個別のご相談も承っております。提携の司法書士や税理士と連携して相続手続きを支援しております。お気軽にお問合せください